どうもイチニノです。今回は発達障害の告知、伝え方について、いつ、どのように、本人への伝えるかなど、書いていきます。というのも我が家でも小学生長女に、今まで伝えていなかった発達障害グレーゾーン及び境界知能について告知しようとしており、現在各所に相談、意見出しをしている最中、、、とかなりタイムリーな状況です。なにか参考になれば嬉しいです。ではどうぞ。
告知は必要?
そもそも告知は必要なのでしょうか?結論からゆうと発達障害の特性が多岐に渡っている為、ケースバイケースであり、どちらとも言えないですよね。そして本人に伝えるかどうかは親の意向に委ねられています。早くは幼稚園の頃から伝えているというケースや、本人が気づくまでは伝えないというケースなど、告知のタイミングって本当にさまざま。そして難しい問題です。
告知のタイミング
きっかけは学級選択
なぜ我が家では今、小学生のタイミングで障害について伝える事にしたのか。きっかけは特別支援学級という選択肢を長女本人にも認識、また可能性として広げておきたかったからです。
特別支援学級
小・中学校に設置されている障害のある児童生徒を対象にした少人数の学級。自立活動や学習、生活の困難を克服するために設置され、児童生徒一人一人のニーズに応じた特別な指導を行う場。
対象障害種:知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者、弱視者、難聴者、言語障害者、自閉症者・情緒障害者
告知なしの状況ではおそらくヘルプとして特別支援学級を視野に入れることは難しそうにみえているので、自身の特性を知ることで、成長と共にどういった環境で学びたいか選択肢を持てるようになれればと思っています。
自己肯定感低下の懸念
ここ半年で長女に見られたのは、自分には『できない』『わからない』と諦める姿です。少しの躓きにも諦めてしまうことがしばしばありました。そういった長女を見ていて、周りと自分を比べられるようになったのだなと成長を感じると共に、このまま自分にはできない、やれないと自信をなくし自己肯定感がどんどん低くなっていくことに懸念を感じました。
ワーキングメモリや処理速度の低さからどうしても起こってしまう特性としての出来事にただ『自分はバカだから』と一括りにし諦めてしまう。そういった自己肯定感の低下が告知によって本人の腑に落ちたり、納得に繋がり、別の方向に感情が変換されればと思っています。
生きやすさを得る
これらのことから、私たちはそろそろ告知をするタイミングなのかなと思っています。(特に告知をしてもしないでも変化がないのであれば、意外と今は安定している状態なのだと思います。)しかし、障害を伝えることによって、本人の生きづらさや、困難が改善され、少しでも自信を持って生きていくことができるのであればそれは告知を検討するタイミングなのだと思います。
特に長女にも見られた自分と他人を比べることができる、自他の理解が進むことはいいきっかけのように感じます。自分のできなさに理由づけされることは救いになるのではないでしょうか。
どのように伝えるか
次に問題なのは、どのように告知するか。これは未だに夫婦間で迷っていることでもあります。伝え方によっては障害という事実を受け入れられず、さらに自分を卑下するようになってしまう可能性がなくもありません。自分という人間を知ることは必ずしもプラスに働くものではないです。でもそれはみんな同じですよね。得意なことがあれば、不得意なこともある、個性と発達障害は紙一重な面もあると思います。そんな風にある意味みんな同じなのだと上手く伝わればいいのですが、捉え方は親がどうこう操作できることではないですからね。『そんなこと聞きたくなかった。』そう言われてしまうことも考え、それすらフォローできるようにしなければいけないなと思います。
発達障害を告知しなくていもいい社会
発達障害が認知され、その割合も増えてきているとはいえ、まだまだ発達障害をもつ子供たちの生きづらさは解消されないのだろうなと改めて思います。一個人としての課題もあり、さらに他と関わることで課題は増えていく、本当に大変だなぁと長女を見ていて感じてしまいます。発達障害や境界知能について、さらに理解を深めていくことがこれからもっと求められていくのだろうなと。そしていつか障害を告知しなくとも、理解し合える社会になればいいのになと思いました。
ということで
発達障害を子供にどう伝え、告知するかについて、我が家のケースを書きましたがいかがだったでしょうか。告知のタイミングは特に正解がないこともあり、親御さんが悩まれる問題の一つではないでしょうか。私の性格上、心配が優ってしまい、なかなか環境の変化を選べずにいますが、きっと大丈夫だと子供のことを信じて話してみようと思っています。また報告させてください。ではでは。
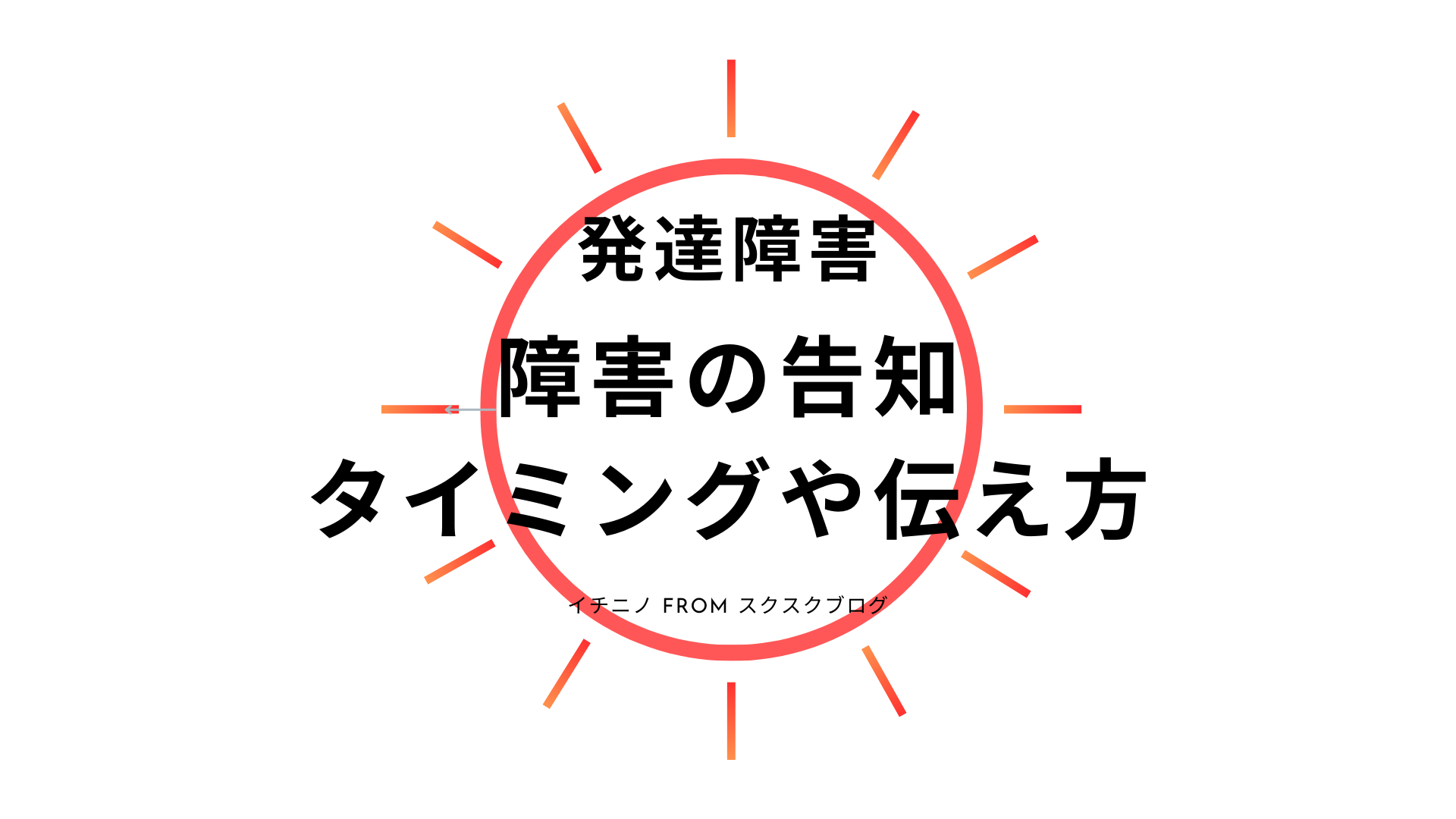
Comment