特別支援教室の授業参観の続き
イチニノです。前回アップしております、発達障害グレーゾーン、境界知能の小学生長女の特別支援教室の授業参観のブログの続きになります。1時間目のグループ学習を終えて、2時間目の個人指導の内容がメインになります!ご自宅でも取り入れられることも多くあると思いますので、是非参考にしていただければ嬉しいです。ではどうぞ!
個人指導開始
休憩をはさんで一緒にグループ指導を受けていた子供達も散り散りと別の教室に移動し、先生と1対1で各々授業にとりくみます。そういえば、この特別支援教室は教室自体にも一つ工夫がしてあります。それは廊下側に向けた窓がないこと。注意力が散漫になったり、他への気の移りが起こらないよう物理的に外の世界を遮断し、集中できる環境を用意していただけています。
さて本題の個人指導です。現在ついていただいている先生は女性で、一年生の頃もお世話になったことのある先生なので長女も安心して授業に取り組んでおります。
内容としては
①呼吸
②目の運動
③書いてみよう
④ボール運動
⑤文を作ろう
⑥自分日記
⑦ゲーム といった流れで授業が進んでいきました。
かなり項目は多いですが一つ一つの学習はとても短く、集中し続けると疲れてしまう長女の特性を加味頂き、やる気や出来具合に合わせてその長さも調整しながら進めて頂いているのが見ていてよくわかりました。
呼吸
3秒大きく吸って、3秒大きく吐くこの呼吸を5回繰り返します。
今でも授業に入る前の出来事や体調によって気分が落ち着かない事があると聞いていたので、恐らくそういった感情や気持ちをコントロールし、自分を落ち着かせる方法を覚え、癖付けをしているのだと思います。
目の運動
この学習がとても面白いと感じました。使用されていたのはビジョントレーニングボードという、透明なA4ぐらいの下敷きのようなボードです。外枠にそってひらがなと数字、内側に1から20までの数字、中央付近に縦5×横10の小さな数字?か文字?の羅列があります。このボードを中心に先生と長女が向き合う形で使用していきます。
取り組んだ内容は
❶外側不規則に並べられた数字とひらがなの読み上げ
❷内側にある数字の中から先生が読み上げた2つの数字を①正順にタッチ②逆順にタッチ
❸内側にある数字の中から先生が読み上げた3つの数字を①正順にタッチ②逆順にタッチ
これによって眼球運動、目と手の協調性等の訓練はもちろんですが、ワーキングメモリの強化が期待できるなと感じました。与えられた情報を頭の中にインプットし、正確にアウトプットする。またインプットした情報を正確に処理して(逆順)アウトプットすることで、聞き取る力、また記憶を保持する練習になっいます。長女も初めての取り組みだったようですが意外と上手に答えることができておりびっくりしました。
書いてみよう
ここでは、先生が読み上げる文章を聞き、各文章の頭の文字を書くということを行っていました。
ex)「明日は、弟の誕生日です。ケーキを買いに行きます。」の場合、答えは「あ」と「け」
何回かやったことがあるようですがそのルールに不安があったのか、先生に答えが正しいかどうか確認しながら進めていました。また途中からは頭の文字から頭の言葉を書きましょうへと変更指示があり、そちらにはすんなりと馴染むことができていました。
ボール運動
柔らかいボールを使った運動です。最近テレビでみたバレーボールに少し興味があった長女はノリノリです。ボールを真上に上げている間に拍手を1回。できたら2回と増やしていきます。長女大苦戦!!ボールを上手に真上に上げることが難しのか顔面にボールが落ちてきます。掴むタイミングも早くしなくてはいけないし、ボールが落下してくる恐怖もあるしで目を開けておくのも大変そうです。ただ、大苦戦の割には「もう一回、もう一回やってみる」と一生懸命に取り組んでいました。結構コツを掴むのが苦手で何回かうまくいくのですがその時の動きを再現するのに時間がかかっている様子です。そこはもう少し自分のことを理解し始めると楽になってくるのかななんて考えています。
文をつくろう
プリントの教材を使用し、書かれた絵を元に文章をつくり、読み上げます。
音韻とてにをはがまだ弱いのでじっくりと時間をかけて今も取り組んでいます。特に音韻認識と音韻処理については一番力を入れてもらっているところでもあります。
音韻認識:言葉が何文字でできているか、また使われている文字はなにか、はじめの文字はなにか、など言葉の音に着目し操作できる力
音韻処理:文字記号を視覚的に認識した上で音に変換し、その音の連なりから一つの言葉として理解し、さらに言葉の連なりを一つの文章として理解する力
LD(ディスレクシア)の特性としてこの音韻認識や音韻処理の弱さは当てはまる人が多く、通常だと小学1年生ごろには確立れていたいところですが、なかなか難しい現状です。似た音に惑わされたり、書き損じをしたりと、未だに間違うことも多いですが、何度も繰り返し学習することで定着をめざしています。
自分日記
自分が書きたいことを日記形式で書きます。先ほどの文を作ろうでは与えられた課題に対して文を作っていたのに対し、次は自身の気持ちや考えを自分で1から文章を作っていきます。昔は何書けばいいのー?となかなかうまく言葉が出てこなかったり、内容に「どんな〜」「何を〜」といった修飾語を使うことが難しかったのですが、家でYoutubeの感想を書いてることもあり経験が積まれ、以前より少しずつ長い文章を書けるようになっていました。時々主語が抜けたりもしますが、それでも誰かに伝えるための文章を書くことができるようになったなと感じた時間でした。
ゲーム
カードを使って、相手からワードを引き出すゲームをしていました。
ex)うさぎのカードを引いた場合。
『うさぎ』という言葉を使わずに相手に「動物です」「かわいいです」「ぴょんぴょんはねます」などヒントとなるワードを出し、カードに書かれたワードを当ててもらいます。
こちらは語彙力の強化を意識していただいているのかなと思います。長女の場合、日常に馴染んだ言葉に関しては問題ないのですが、身近でない言葉(単位や素材の名前などなど)については定着するのに時間がかかります。通常、新し言葉を聞いた際、その言葉の用途や意味を自然と頭で分類し、蓄積させていっているらしいのです。が、長女の場合はそうはいきません。言葉自体に興味をもち、意識的に覚えよう、覚えたいという思考が必要となります。
ほめほめタイム
今回は時間が足りず実施されませんでしたが、自分がよくできたところを褒める時間になります。
【自分で自分を褒めてあげる、認めてあげる】自己肯定感が低くなりがちな発達障害グレーや境界知能の長女はもちろんですが、本当は誰しもが必要なことなんだろうなと思います。自信をもつだけで行動が変わったり、周りへの印象も変えることができると私は思っています。そういった時間を少しでも作ろうとしていただいているこの時間は本当に有難いです。
余談。。おもしろかったゲーム
1時間目が終わると通常の授業と同じく休み時間があります。長女は主に個人指導の先生とゲームを楽しんで過ごしているようで、今回も先生と長女、あと私も一緒に【GO SLOW!ゆっくり行こうぜ!】を楽しみました。
【GO SLOW!ゆっくり行こうぜ!】
簡単にゲームを説明。4人までプレイ可能で、プレイヤーは各々自分のコマ(カタツムリ)をもち手持ちカード(2枚)に従い一直線な盤の上を進めて行くゲームです。しかしこのゲーム、他のゲームと違い、一番最後にゴールに辿り着いたプレイヤーが勝者になります。ゲームの名前通りいかにゆっくり進むかが重要になっているのです。また1マスに2プレイヤー滞在できないというルールがあるため、ところてん方式で押し出されていくのもおもしろい、かなりカード運に左右される面白いゲームでした。
特別支援教室ではゲームを授業に取り入れられることも多いため、かなり充実のラインナップです。勉強勉強しない環境に子供達は過ごしやすいだろうなと改めて実感しました。
授業参観終了
そうして無事授業参観は終了しました。長女は終わるや否や、教室でやることがある!と出ていってしまいましたが、よく頑張っていたなぁと嬉しく思います。
まとめ
今回は2回に渡って【特別支援教室】について授業参観を通じて書きましたがいかがだったでしょうか?利用するには教育委員会に相談したりと少し手間がありますが、お子さんの行動や勉強について不安がある方は担任の先生に相談しながら利用を検討してみても良いのかな?と思います。
子供の教育方針についてはさまざまな考え方があり、私も節目節目で悩みますし、将来を考えると不安にもなります。でもどうなるにせよ情報を集めて知って知識を持っておくこと、どうなってもいいように可能性を広げておくことがきっと子供のためになるのではと思います。少しでも参考になれば嬉しいです。
ではでは

“knowledge is wealth.”
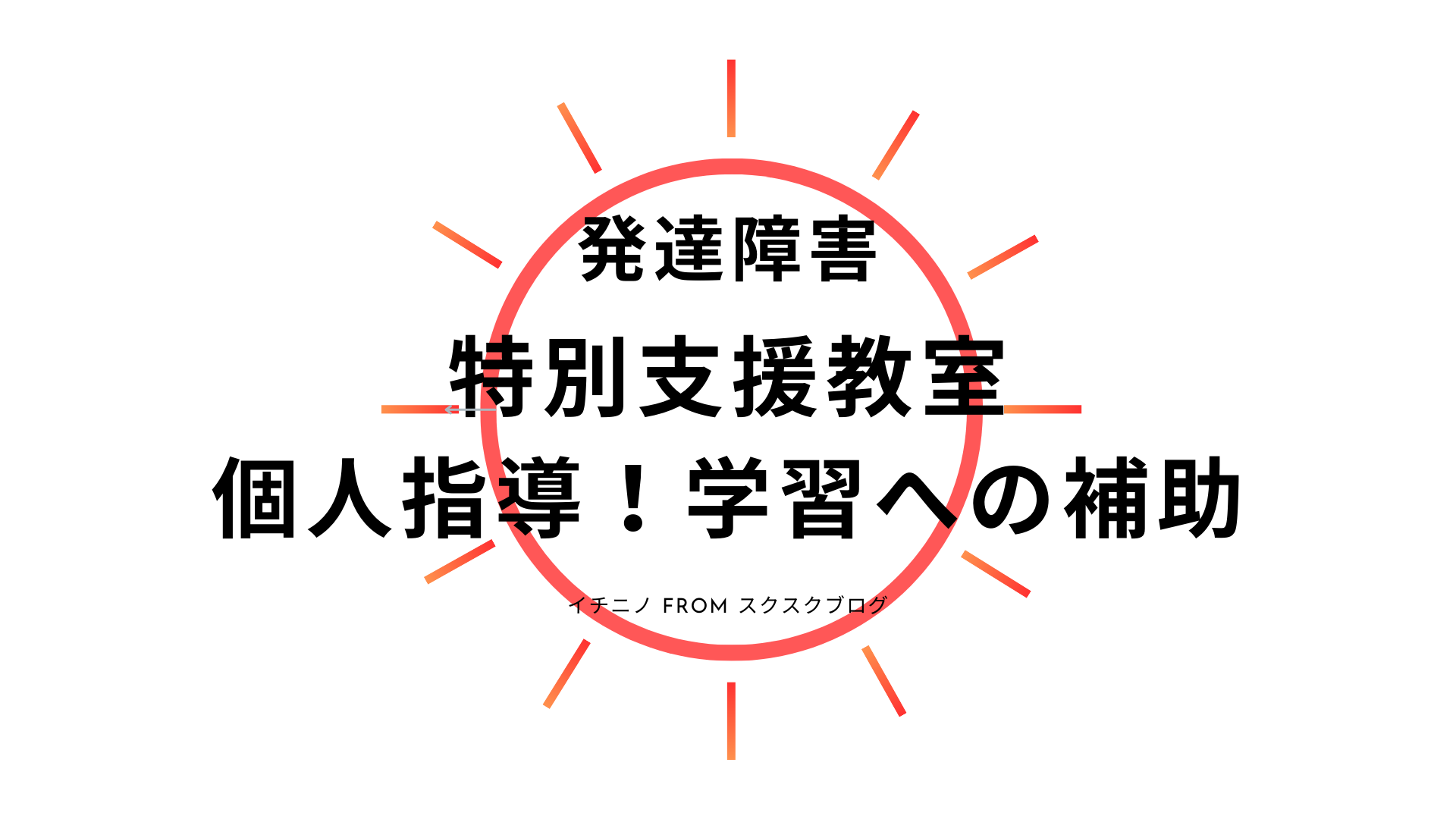
Comment