どうも、発達障害グレーゾーン・境界知能の小学生長女をもつハハ、イチニノです。今回も、前回に引き続き小学校での困りごとシリーズ第一弾!授業中の立ち歩きに関してです。(まだ読んでいない方は是非▶︎こちらを読んでから見てください)ではどうぞ。
前回の振り返り
学校の担任の先生との面談、長女との話し合い、と、それぞれに立ち歩きについてのヒアリングをし、1年生の時には指摘のなかった授業中の立ち歩きがなぜ始まったのか、いつどの様な時に起こるか、そして長女自身はどの様に考えているかなど原因と理由がある程度分かり、再度学校との配慮について話し合いの場を持つことになります。以下続きです。
再度面談
まず私から、立ち歩きに関して周りへの迷惑や授業の進捗にも影響があったことも含め大変申し訳ない旨伝えた上で、今回長女が立ち歩きに関してやってしまっていた理由や原因について説明させてもらいました。先生としても行動の理由と原因がわかったことで納得がいったようで、その上でどの様に配慮をしていくべきか、また長女自身もどのような対策をしていく必要があるか、学校と家庭で役割の整理をしました。
まず私から、
家庭としては立ち歩きはどんな理由であれあまりよろしくないと考えているので長女には【立ち歩きをしない】ということを2年生通しての目標とした。また立ち歩きについて考え、出来事に対してあまり神経質にならずに学習が難しくても、周りがうるさくても適度に受け流せるようにしたり、そうなる前に対策したりしようという話をした。
その上で立ち歩きがしたい状況になった場合、必要があれば先生にヘルプを出すよう伝えた。もし長女が気持ちのリフレッシュやコントロールする必要がある場合は立ち歩き含め、一度教室を出るなど何らかの対応ができるようにしてほしい。
先生へのイメージに関しては大変お手間をかけさせてしまうけれども、長女が慣れるまで、懐くまでの間、少し多めにコミュニケーションをとってもらえないか。
という3点お話をしました。
先生からは
立ち歩きについて、学習の導入や一斉指示といったところで『遅れ』が生じたことにより難しさや諦めになっている可能性もあるので、今より早いタイミングで先の動きを伝えるなど声掛けをし、難しさを少しでも減らせる様配慮を始めようと思う。
周りの声や音に関しては確かに小学2年生なので、かなり騒々しく、担任としてもうるさいと感じている。今後クラス全体としても話し方・聞き方を学習してくので、改善に繋げていきたい。
最後に長女との距離感に関して今後コミュニケーションを増やし信頼関係が築ける様に努めたい。
と、ありがたいお話し頂けました。
まとめ:配慮と対応
◉立ち歩きの原因を理解し、対策方法を考え実践する(子)
◉立ち歩きをしたくなったら先生に相談、ヘルプを出す(子)
◉学習や一斉指示は早いタイミングで声掛けを行う(学)
◉周りの音や声についてはクラス全体として話し方・聞き方を学ぶ(学)
◉長女、先生間のコミュニケーションを増やす(子・学)
その後の経過
その後、すぐにとは行かなかったですが、この面談後、かなり立ち歩きの頻度は減りました。その理由としてはまず家庭で話し合いをしたことで、長女自身も自分の困りごとに気づくことができ、その対策を一緒に考えることができた。また先生との関係性が良好になり、困っていることや嫌なこと、質問したいことを伝えられるようになった。ことで立ち歩きが少しずつ必要無くなったのだと思います。
そして学年が上がり3年生になった頃には全くそういった指摘は無くなりました。
親子でできること
立ち歩きをしていると聞くと、親としてはかなり焦ります。周りに迷惑はかけていないか、授業の邪魔はしていないか、お友達に変に思われてはいないか。色々な考えが頭をよぎります。
ただ、ちゃんと子供と話してみるとそこには子供なりの理由があるんだなと思います。(長女の様にうまく伝えられない年齢の時は内容を汲み取るのが相当難しかったりもしますが。。)ちゃんと困っていることを解決しようとして動いているのだなと。なので立ち歩きをしているという事実よりも、大事なことはどうしてそういった行動になっているかを一緒に紐解き、解決策を出すことだと私はこの時学びました。
時には問題行動も必要
発達障害の子供たちの問題行動と言えるものはたくさんありますが、ただ我慢が足りないとか指示が通らないとか、そんな簡単なものではなく、もっと複雑なんだと思います。自分をコントロールする為だったり、SOSのサインだったり本人たちもうまく行かないことに困っているのかなと。またそういった問題行動の一つ一つをしらみつぶしに改善することが必ずしも本人のためにもならないのだなとも思いました。長女の場合は周囲の騒がしさから心を落ち着かせるために立ち歩きをしていました。それを無理やりにでもしない様にすることはできますが、それでは本人にずっと落ち着かない空間と時間を強要することになります。特別扱いは必要ないですが配慮は必要です。発達障害をもつ子供たちには自分を落ち着かせるためのルーティンがあると良いと言います。ちゃんと心の逃げ道を作っておくことで安心が生まれ問題行動が減っていったりと良い方向に向かう可能性も多いのかなと思います。
ということで
2回にわたって小学生の立ち歩きについて長女のケースを例に書かせてもらいましたがいかがだったでしょうか?本当に発達障害といっても色々な特性の子がいるので参考にならないかもしれませんが、少しでも改善のヒントになれば嬉しいです。ではでは
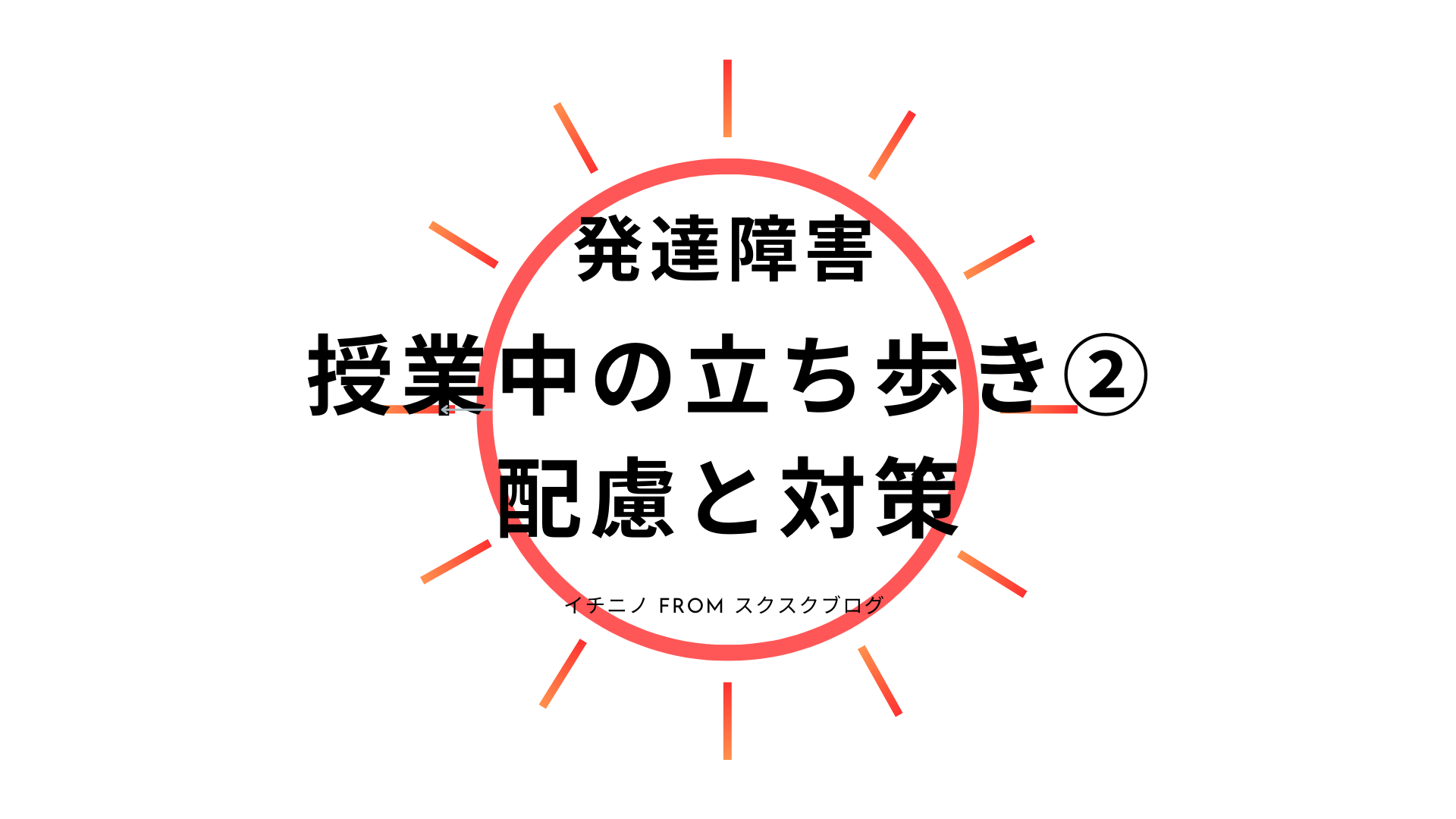
Comment