特別支援教室の授業参観
イチニノです。発達障害グレーゾーン、境界知能の小学生長女の特別支援教室の授業参観に行ってまいりましたので、そちらの様子や、内容など書きますね。学校では偶然にも担任の先生ともお話しすることができたので、クラスでの様子も聞くことができてとても充実した時間となりました。ではどうぞ!
特別支援教室
長女は小学生から週1日2時間、特別支援教室で授業をうけています。そもそも特別支援教室という名前が聞きなれない方もいるかと思うので軽く説明します。(うちの地域の呼び方だったり、仕組みだったりするのかもしれません)
▶️特別支援教室
発達面や情緒面などで課題を持っている子供たちを対象に、各々の特性に合った指導や教育を受けることができる場。※在籍は通常学級。
長女の場合はグループ指導と個人指導で各1時間ずつ指導を受けています。時間で見ると少なく感じますが、年間指導計画を学期ごとの面談を通して作成して頂けますし、なんといっても、通常学級では手の届かない部分であったり、やむなく見落とされ、放置されてしまうといったところを一人一人の成長速度や必要性に応じて、きめ細やかに配慮をしていただけるので学校生活においてはとても貴重な時間になっているかと思います。また本人としても担当の先生と密な関係を作ることによって安心して過ごせる時間の一つになっています。
先生さん曰く、日々特別支援教室の需要は高くなっているので、年度替わりに関わらず、学年途中でも特別支援教室の利用人数は増える傾向にあるのだとか。その影響からか、昨年度は一緒に受けるお友達が年度途中で変わったりもしていました。
授業参観開始!
の、前にまず手始めに、、、
私が授業開始5分前に教室についていたのですが、その時点で教室にいたのは長女のみ。(これはきっと特別支援教室歴が長いのでしっかり習慣になっている証拠ですね)他の子達はチャイムが鳴る前後でわらわらと集まり始め、また先生が迎えにいく場面もあったりと、授業開始できたのは本鈴のチャイムから5分経った頃でした。(長女も好きな授業には積極的なので移動教室も難なくこなすのですが、いかんせん自分の苦手な授業や他に気を取られてしまうと見事に動きが遅くなります。体育の授業の準備体操にほとんど参加したことがないというのを聞いた時はびっくりしたもんです。。)
【授業参観】1時間目:グループ指導!!
さて本題の授業参観です。1時間目はグループ学習の時間でした。このグループ学習、今年の長女の場合は2〜4年生の男女4人で編成されていますが、学年が変わるごとに、学年も人数も組み替えられるので、今年はこのメンツといった感じでしょうか。学年の縛りなど取り払うことによって上の学年には責任やリーダーシップを意識させたり、下の学年には人に頼ったり甘えても問題ないのだという環境を体験する場としてメリットも多いと思います。(もちらろんうまくいくことばかりではないと思いますが、そこは試行錯誤ですよね。)
1時間目スケジュール
(グループ指導:男女4人、学年は2〜4年生、先生4名。)
・はじめの会
・体を動かそう!
・ゲームタイム
・終わりの会
メインの先生が1名リーダーのようにして進行し、その他の3名が個々の補佐や記録をしながら授業が進められます。またちゃんと毎回日直さんが決まっていて、始まりと終わりの進行をしてくれます。なんだかとても懐かしい気がしましたぁ。
【グループ指導】体を動かそう!
早速、みんなで運動タイムです。この運動タイム、発達障害を持っていると体感が割と弱かったり〜、という理由で組み込まれているのもあるのだと思いますが、キーになっているのは【一斉指示】かなと思います。
【一斉指示】小学校や保育園など、集団生活の中で先生が生徒(子供達)に対して伝える指示
運動をするにあたっての流れ
リーダーの先生から「まずこれ、次にこれ、その次にこれをしてください。はいどうぞ。」といった感じでそれぞれの指示を聞いて実行に移していきます。
①準備としてやるべきことを3つ
②運動の内容を4つ
③回数やそもそもの社会的ルール(ぬかさない等)など確認事項を3つ
意外と各々にボリュームがあり、それを先走りせずに最後まで聞き、行動に移すということ。また指示を抜けなく順番通りに行うということ。割と簡単にこなしてしまうお子さんもたくさんいると思いますが、これが発達障害グレーゾーンの長女は大の苦手です。
発達障害グレーゾーンと一斉指示の通りにくさ
長女の話になりますが、長女は聞く態度はとても上手ですが、全てを記憶し、行動に移すことがまず難しいです。(これはWISC検査のワーキングメモリの低さからも立証済み)しかし、要因はそれだけではなく、
❶指示の中に知らない、分からない言葉が含まれている
❷指示に対して見通しが立てらない
❸周りの音や環境に集中ができない
❹自身の気になることが他にある(目についてしまう)
❺結果「指示を出される→それが(指示通り)できた!」という成功体験が少ない。
など、多くの要素が絡み合って、なかなか思い通りに指示に従うことが”難しい出来事”になってしまっています。
しかし、特別支援教室は一貫してマイナスワードが少なく、できたことを褒めてもらえる場です。それぞれのファクターでつまずきながらも先生が軽くヒントをくれると思い出せたり、「忘れたー」と素直にヘルプをだしたり、今何をするべきか、声掛けをしながらみんなで取り組むことで成功体験を積むことができているのだと思いました。
【グループ指導】ゲームタイム!
そして、ゲームタイム。こちらは前回からみんなでやっているゲームのようで、チーム戦で宝石を奪い合うゲームをやっていました。このゲームでのキーは【気持ちのコントロール】かなと思いました。というのもあえて勝敗のつくゲームをやり、「勝っても威張らず、負けても怒らない。」そういっためあてを共通認識でもち、自分の気持ちと相手の気持ちがあることを学びます。自分の嬉しい気持ちや悔しい気持ちを認めつつ、周り(相手)に対してどのような対応や表現をすればいいか、を実践を通して身につけていきます。
長女も特別支援教室に通い始めた頃は、負けるのが悔しくて勝ち負けのつくゲームに参加することができなかったり、負けた時は悔しくて泣いたり怒ったり不機嫌になってしまったり、うまくいく時、いかない時を何度も繰り返してきていました。しかし今回の授業では、敵チームに対してはしっかり目当てを守りながら、さらにチームの人との相談の場で意見を押し付けるのではなく、ちゃんと相談になるようにどういった声掛けをすればいいか、どう伝えるかを確認しながらゲームを進めていました。いつまでも幼いなぁと勝手に思っていましたが、本当に成長を感じます。
やはりそうなれたのも先生の「その伝え方いいね!」「上手だね」とうまくいったコミュニケーションに対して見逃さずしっかり褒められることが大きいと思います。自分ができた!という肯定感を持てることが次もやりたい!できる!という自信につながっているのだと思います。またゲーム中はみんな楽しそうに過ごす場面が多く、やはり人は褒めると嬉しくなるし、やりたくなる。単純なことなのに親としてなかなかできずにいたりするなぁーと改めて反省でした。
2時間目は個人指導!
最後に終わりの会を日直さんが進めてくれて、グループ指導は終了です。
気持ちが乗らなくて上手に参加できない時もあるようですが、この日は本当に立派な姿を見せてくれました。また驚いたことに苦手としていた男性の先生とも仲良くちょっかいをかけながらコミュニケーションをとっており、あれ?こんな子だっけか?と新しい一面も見ることができました。
次の2時間目は個人指導となります。かなり長女の特性に合わせた指導になるのですが、目の運動なども新しく取り入れられており、こんなこともやっているのか〜の連続でしたので、是非次も参考に見ていただければ嬉しいです。ではでは

“Before you know it, you’ve become an adult.”
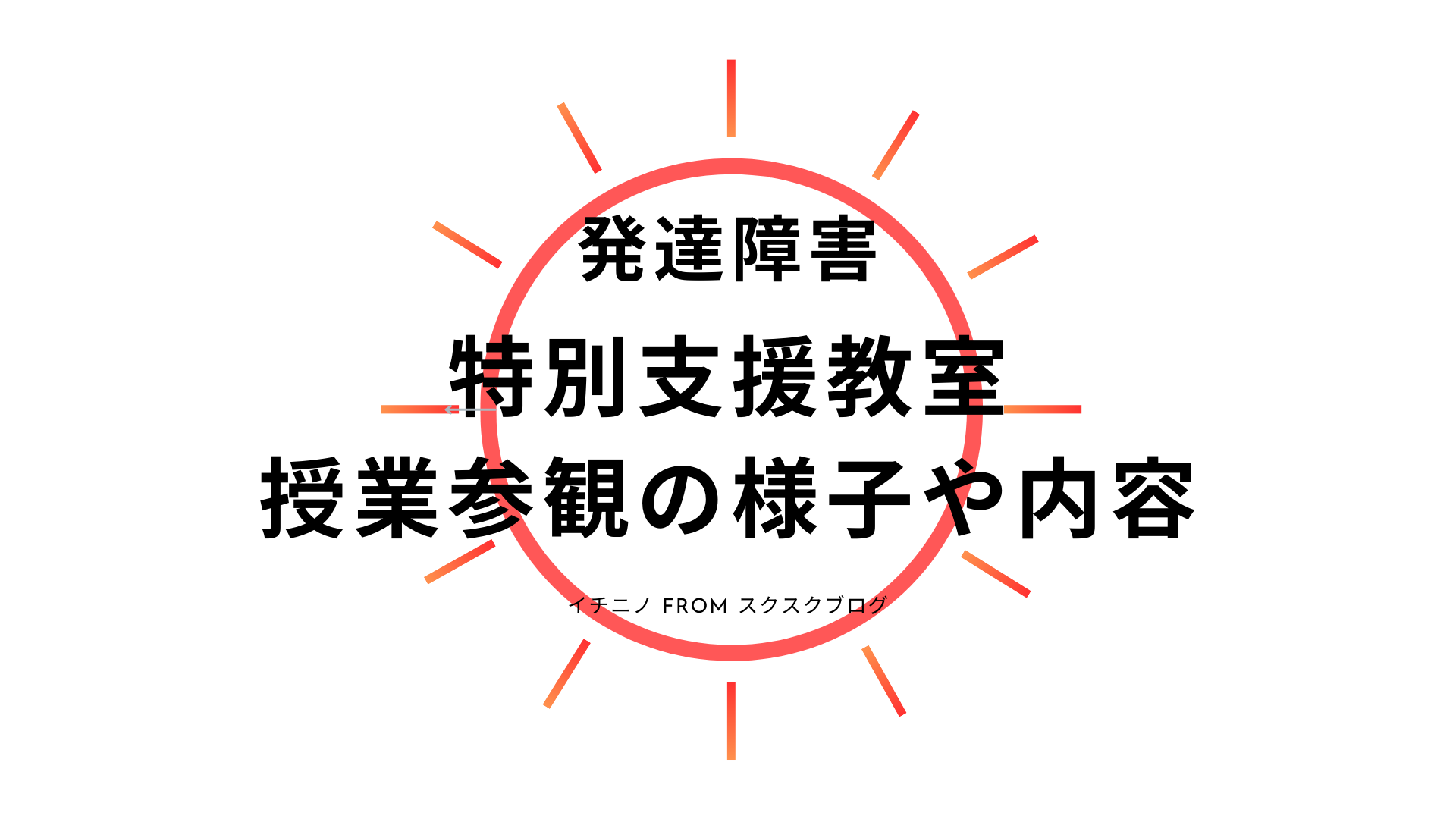
Comment