イチニノです。発達障害グレーゾーン・境界知能の長女の学習や課題に取り組む際、わかっている特性の一つ『場当たり的』というワードにについて書きたいと思います。
同じような課題を持つお子さんの参考になれば嬉しいです。ではどうぞ!
境界知能の特性『場当たり的』とは
WISC検査
まず、長女の特性の一つとも言える『場当たり的』といわれたのは小学2年生の頃に受けたWISC検査のフィードバックのときでした。まず簡単にWISC検査の概要です。
長女は小学2年生の時に担任の先生より勧められ、検査を受けました。これまでの発達検査では新版K式発達検査や知能検査の田中ビネー検査を行ってきましたが、この時が初めての検査でした。
WISC検査
「言語理解」「知覚推理」「処理速度」「ワーキングメモリー」の4つの指標とIQ(知能指数)を数値化する検査。この4つの指標から個々の得意、不得意(苦手)を知ることにより、より良い支援の手がかりを得ることを目的として行う検査になります。
場当たり的とは
WISC検査の後、指導員さんよりフィードバックが行われます。その際に指摘されたのが『場当たり的』な処理をしているとのこと。なぜそのような判断になったか、こちらも簡単に検査内容を教えていただきました。
『場当たり的』と判断された検査の内容
一言でいうと、単純作業的な課題をどれだけこなせるか「処理速度」を測るテストです。
まず一枚のプリント紙が渡されます。
プリント上部には【指示ルール】が書かれており、それに従い複数の問いをできるだけ多く解きます。例えば、【Aと書かれていたら○、Bと書かれていたら×、ABと書かれていたら△】の記号を当てはめなさい。という指示ルールに従い、羅列された単語に対し○×△のマークをチェックしていくといった問題です。※かなり前なので、そんな感じとてして捉えていただければと思います。
通常このような問題が出された時、できるだけ多く問題を解くことが求められることもあり、まずどのようにこの問題を解いていくか、取り組む上での工夫やコツのようなものを考え(正解・不正解はさておき)各自、戦略のようなものを立てるのだそうです。
![]()
発達障害のお子様の自宅学習をサポート【すらら】![]()
しかし長女の場合は、問題に対し指示を確認しては解き、また指示確認をしては解きというように、とりあえず一つ一つ問題を解いており、それが『場当たり的』な解き方をしているというフィードバックとなりました。確かに、指示ルールを問題一つ一つに対し確認する必要性はないですし、戦略は全くなく解いてしまっていますよね。
算数の文章問題でのつまづき
この『場当たり的』というワード、WISC検査後は特に取り上げるタイミングもなく、忘れ去られていたのですが、小学3年生の頃、算数の文章問題で出くわすことになります。意外にも算数の計算に関しては足し算、引き算、掛け算、割り算と、通常の進捗に乗って学べていた長女。なので文章問題も問題ないかと思っていたのですが、これが大間違い。長女は『この問題で使うのは何算か』ということを飛ばして、とりあえず分けると書いてあれば適当に5ずつに分けてみたり〜、足してみたり〜引いてみたり〜、と計算式を考えずに『場当たり的』に処理しようとしていたのです。
場当たり的から策略的への軌道修正
この算数問題、解決するのはとても簡単でした。内容の把握が出来ていたこともあり、『この問題は何算を使う?』と聞けば正確に〈+−×÷〉を選ぶことが出来ていたので「じゃぁそれを使おうか。」と話しただけです。あとは数回問題を解き、その際はしつこく「この問題が何算か」を意識させる・解くを繰り返すだけで考え方が身についたようでした。
そもそも『場当たり的』な処理は決して間違ったやり方をしているわけではなく、とても遠回りをしている状態なのだと私は感じています。なので、内容ややるべき事をちゃんと正しく理解をできているのであればコツや工夫を伝えることで『場当たり的=遠回り』から『策略的=近道』へと変えることができたのだと思います。
ということで
今回は境界知能の特徴の一つ『場当たり的』を長女の例などを取り上げながら紹介してみましたがいかがだったでしょうか?正直こんな簡単に上手くいくの?と思われた方もいるかと思います。が、そこが境界知能の難しさや複雑さなんだろうなと思います。というのも例に挙げた文章問題の件、克服した後に「何がわかってなかった?」と聞くと、「何算か考えるのを知らなかった」と平然と言っており、驚き半分、納得半分。もしもWISCでの『場当たり的』というフィードバックがなければもっと遠回りをしただろうし理解が難しかっただろうなと怖くなったのを覚えています。
もちろん必ずしもこんなに簡単に解決できるものばかりではありませんが、境界知能の特性、癖の把握は問題解決のヒントや近道になるのだと感じた一幕でした。
最後に
子供の現在地を知ることは少し怖いです。また何か受け入れなければいけない出来事や内容があるのではないか、増えてしまうのではないかと思うと気が引けてしまいます。でも子供のことを知ることは本当に有益だなと私は感じています。WISC検査やその他にも様々な検査がありますが、そういったことは理解を深める一つのツールだと思います。もし悩んでおられることがあるのなら、動いてみるのもいいのかなと思います。勝手なこと言ってますね。すみません。
ではでは!

“knowledge is wealth.”
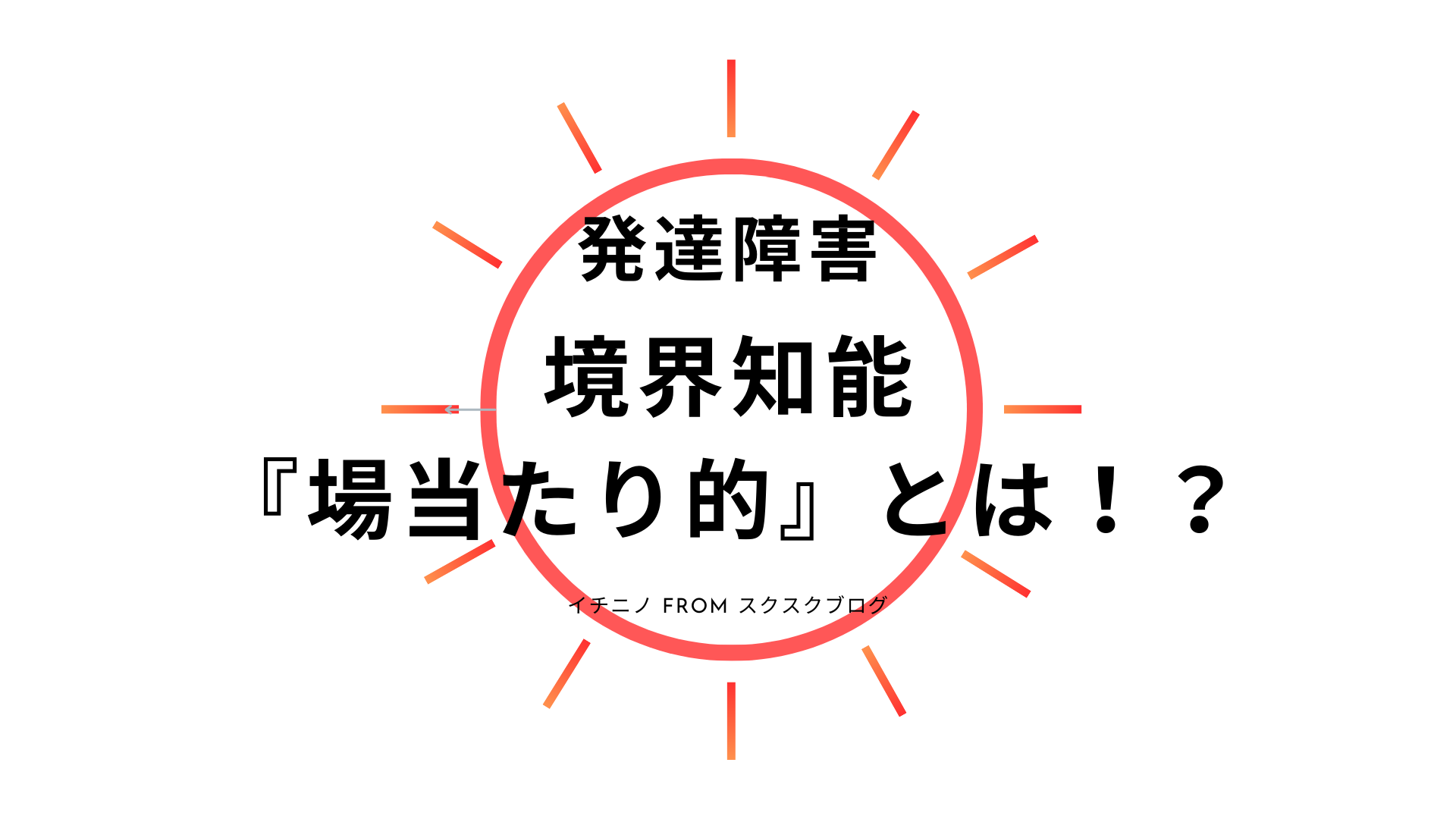
Comment