どうも、イチニノです。前回に引き続き、小学生長女の在籍に関して、通常学級と特別支援教室でどう選択・検討するか。また担任の先生から勧められた際の私の心境や今後どうしていくかについて書いていきたいと思います。ではどうぞ。
頑張っているのに結果に繋がらない
先生が特別支援学級を薦める理由の一つとして、長女がとても頑張り屋であり向上心があることを挙げていただいています。これは私も認めているところなのですが、本当に一生懸命にみんなについていこうと取り組んだり、できるようになりたいという気持ちは人一倍強いと思います。しかし、それがなかなか結果につながらない。ワーキングメモリと処理速度の低さが大きく影響しているのだと思います。そしてさらに言えば結果に繋がるまでの長い時間を費やすことが通常学級では難しいのです。もし何度も何度も時間をかけて取り組んでいればできたかもしれない、できるかもしれない出来事があったのかなと思います。
疲れてしまわないか
またそういった生活の中に置かれる長女の疲れは相当なものだということです。どの時間も頑張らなくてはいけない、でも追いつけない、そういった無理をしているループが延々続いていること。またできないことを目の当たりにしてしまうこと。そういった状況により自己肯定感は下がり、しんどくなってしまわないか心配とのことをおっしゃっていました。
自分と子供は違う
ここまで聞いても、それでもまだ私は特別支援学級を選べないでいます。その理由は、特別支援学級が自分の経験したことのない世界だからだと思います。自分が小学校、中学校と過ごした当たり前の時間を子供に経験させてあげられない不安。そしてその先の未来や将来を考えるとどうなってしまうのか、と、どうしても踏み切れないのです。自分と子供は別の人間。長女にとってのベストな環境は自分とは違う。そうわかってはいても通常学級という場での学びは必要な気がしてしまいます。
子供任せと責任転嫁
私は今のところ、特別支援学級を選択するとすれば、子供がその選択をした時だと思っていました。学校の学習が大変だと言い出したり、学校に行きたくない、楽しくない、辛いとなった場合にやっと判断がつくということです。前のブログに書いた通り、特別支援学級という可能性は残しておいて、最後は、子供自身の意思ありきで決定ができると思っています。
ただ改めて考えた時、うちの場合は【長女に自分の特性や発達障害グレー、また境界知能について告知をしていない】のに、そんな決断やヘルプを子供から出すのを待つというのはあまりにも子供になすりつけた考え方だなとも思い始めました。もう自分で考え、悩み、決定できる歳になってきているのに、自分のことを知らずに、それを求めるのは違っているなと。それは責任転嫁にも思えます。また障害の影響があることも知らずにうまくいかないことで自信をなくしたり、自己肯定感を下げてしまったり、考えれば考えるほどにちゃんと話す必要があるような気がしてきました。
子供への障害の告知
長々と書きましたが、今回書きたかったことはここ【子供に障害の告知をする】ということです。ずーーっとまだ小さい子供だし、障害と言われるのはつらいだろうと思い、長女には障害について何も伝えていませんでした。でももう何もわからない子供ではありません。本人にとってそれが辛い話なのか、腑に落ちる話なのか、正直想像もつきませんが、ちゃんと自分という人間を知ること理解することの第一歩として、話をする必要があるなと思いました。その上で、これからどのような学校生活を送りたいか、将来どうなりたいか、自分でまたは一緒に判断できればいいと思います。
どんな道を選んでも、そこでどう生きるか
子供の将来を考えると、どうしても『普通』というものに縛られて判断してしまいます。でも子供は子供の人生を生き、私ではないです。きっとこれから選んでいくその道がどんな道であろうと、大切なのはその道で夢中になったり、頑張ったり、これが自分にとって正解だったんだと思えるように生きることだと思います。
じゃあ私は親として何ができるのか、結局何もできないまま、強く生きる長女に感心するばかりです。
ということで
二回に渡って発達障害グレーゾーン・境界知能の子供の学級選びについて書いてきました。間違いなく自分の意見なのですが、日々心情は落ち着きなく変わっていきます。自分に何ができるのか、難しい問題です。またこれから子供への障害の告知をする中で、どのように伝え、理解をしてもらうかしっかり考えていきたいと思います。
今この過渡期をどうゆう形で乗り越えるか。ちゃんと向き合いたいと思います。
ではでは
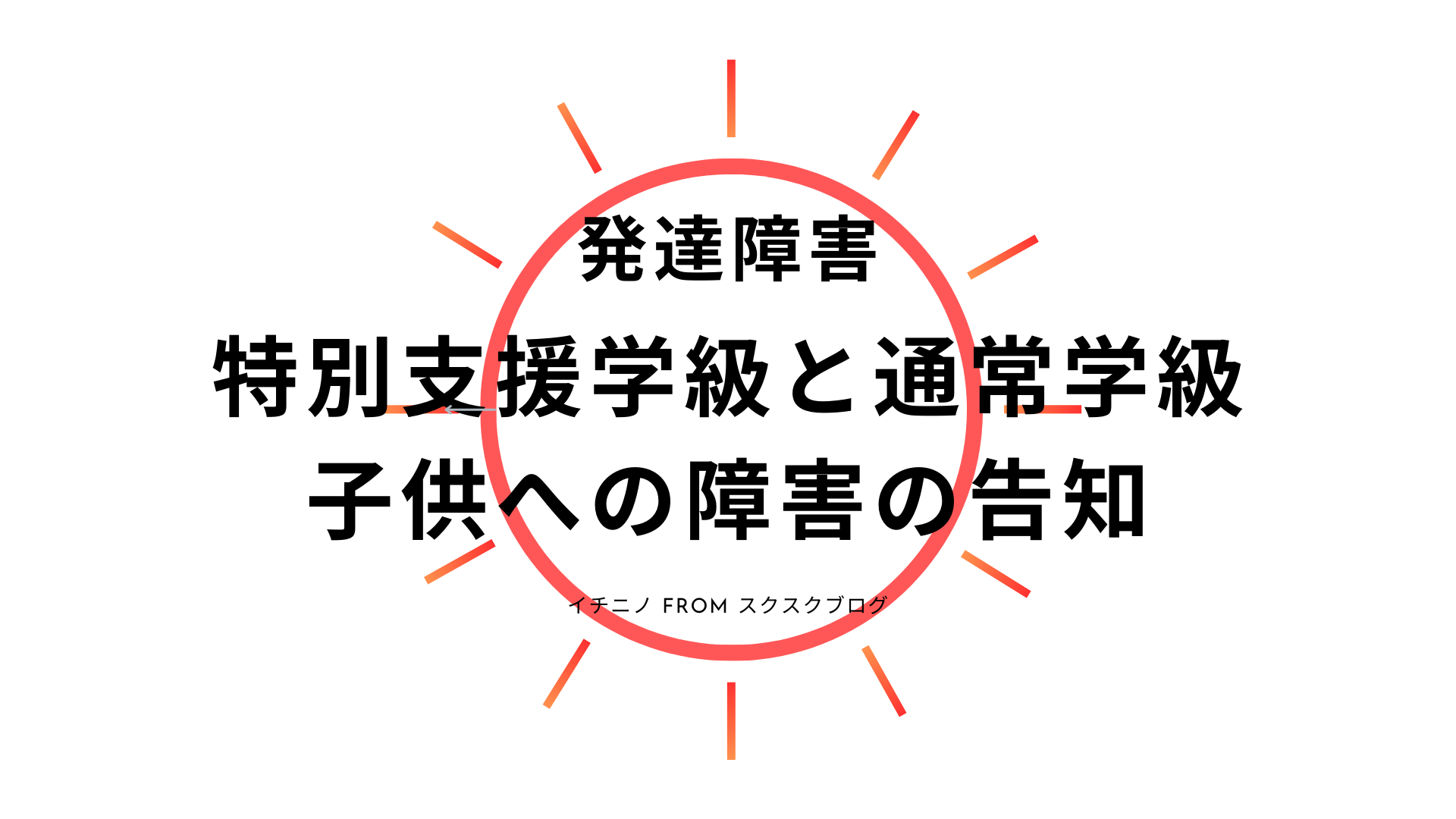
Comment